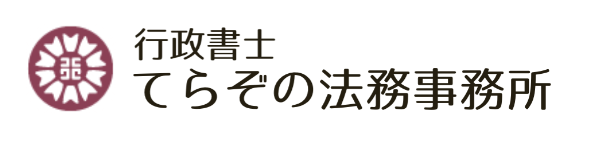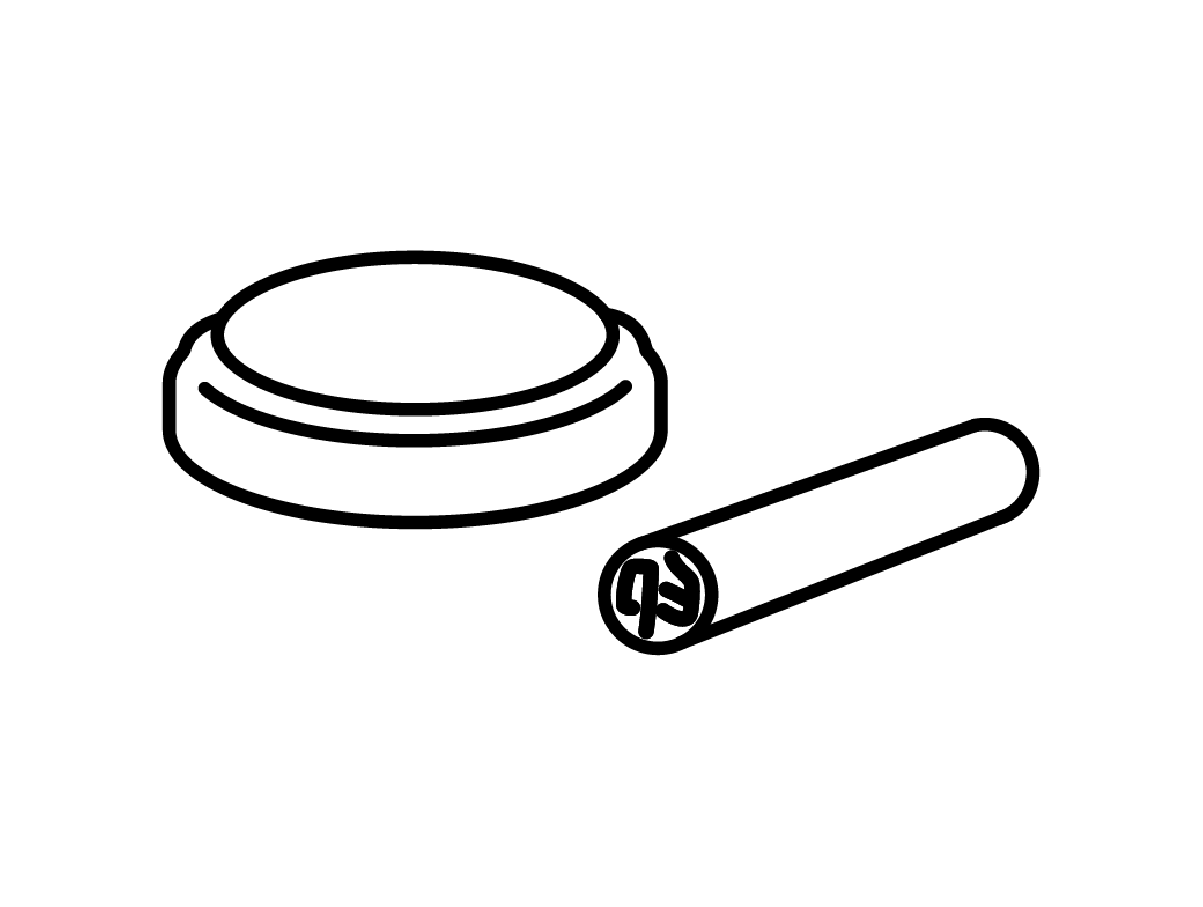- Q1遺言書を書くと、どんなメリットがあるの?
- A
遺言書があると、亡くなった後に家族が「財産をどう分けるか」で揉めにくくなります。
また、あなたの気持ち(「この人に渡したい」「お世話になった人に感謝を伝えたい」など)を形にできます。
行政書士は、こうした「思いの実現」をサポートします。
- Q2遺言書ってどんな種類があるの?
- A
主に3つの方法があります。
種類 特徴 メリット デメリット 自筆証書遺言 全文を自分で手書き 費用がかからず手軽 書き方を間違えると無効になる/紛失リスクあり 公正証書遺言 公証役場で作成(公証人+証人2名) 最も確実で安全/保管も安心 費用がかかる/内容を証人に知られる 秘密証書遺言 封筒に入れて公証人に提出 内容の秘密を守れる 有効性が不明なまま保管されることも
- Q3自筆証書遺言を書くときの注意点は?
- A
- すべてを本人の手で書く(パソコンや代筆は不可)
- 「○年○月○日」と正確な日付を書く(「吉日」は無効)
- 名前と押印を必ず入れる
- できれば封筒に入れ、「開けずに家庭裁判所へ提出」と記して保管
- Q4誰が遺言を書けるの?(年齢や能力の制限)
- A
- 15歳以上なら誰でも可能(民法第961条)
- 成年被後見人でも、医師2人の立会いのもとで一時的に判断力が戻った時なら有効
- 本人の意思が確認できない場合(高齢や病気など)は作成できません
- Q5遺言の内容を後から変えたいときは?
- A
新しい日付の遺言書を作ると、古いものは自動的に無効になります。
たとえば公正証書で作っていても、あとから自筆証書で書き直せばそちらが優先されます
- Q6遺言書を作るときに必要な書類は?
- A
- 戸籍謄本(家族関係を確認)
- 不動産登記事項証明書や固定資産評価証明書
- 預金通帳のコピー
- 印鑑証明書(発行から3か月以内)
- 証人2名の身分証明書(公正証書遺言の場合)
- Q7「遺留分」ってなに?
- A
家族が最低限もらえる取り分のことです。
兄弟姉妹以外(配偶者・子・親)には、法定相続分の半分または3分の1が保証されています。
この取り分を侵害する遺言は無効ではありませんが、請求されると取り戻されることがあります
- Q8行政書士はどこまで関われるの?
- A
行政書士は、遺言書の原案作成や内容のアドバイスを行うことができます。
ただし「税務相談」や「公証人の代行作成」はできません。
遺言執行者(実際に遺言を実行する人)に指定されることも多く、専門的なサポートが可能です
- Q9トラブルを避けるためのコツは?
- A
- 相続人に不公平感が出ないよう内容を検討する
- 生前に遺言の趣旨を家族に伝えておく
- 「付言(ふげん)」として感謝の気持ちを添えるとトラブル回避に有効
- Q10どんな人が遺言書を書いた方がいいの?
- A
- 子どもがいない夫婦
- 再婚して前婚の子がいる人
- 事業を継がせたい人
- ペットの世話を託したい人
- 相続人の仲がよくない人 などは特におすすめです
💬LINEはこちらから⬇️

📱 電話:070-8490-2465
(受付時間:平日10:00~17:00)