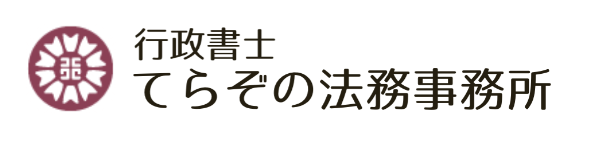離婚後でも安心できる仕組み
2024年の民法改正で「法定養育費制度」という仕組みが新しく作られました。
これは、離婚のときに養育費の話し合いをしなかった場合でも、子どもを育てている親が、もう一方の親に「最低限の養育費」を請求できる制度です。これまで、話し合いがされなかったために養育費が支払われないケースも多くありました。
そこで、子どもの生活が困らないようにするために、この制度が導入されることになったのです。
施行は2026年までに予定されています。
☑いくらもらえるの?
- 子ども1人あたり月2万円(2025年8月時点の案。まだ正式決定ではありません)
- 2人なら4万円、3人なら6万円と、人数分が単純に加算されます
- 支払う側の収入や事情は関係なく、全国一律の金額です
この金額は、生活保護基準を参考にした「最低限の生活費」をもとにしています。
ただし、あくまで暫定的な目安であり、今後の省令や意見募集(パブリックコメント)の結果によって変わる可能性があります。
☑いつまで支払われるの?
法定養育費は、離婚したときから始まり、次のいずれかまで続きます。
- 夫婦で正式に養育費の額を決めたとき
- 裁判所で金額が決まったとき
- 子どもが18歳になったとき
支払いは毎月末に行われます。
ただし、これはあくまで「最低限の額」を保障するものなので、後から話し合いで金額を決めればそちらが優先されます。
☑誰が請求できるの?
請求できるのは「実際に子どもを育てている親」です。
親権や戸籍上の立場にかかわらず、子どもを日常的に世話している側が対象になります。
また、結婚していなくても父親が子どもを認知していれば、同じように養育費を請求できます。
共同親権も選べるように
今回の民法改正では、養育費制度だけでなく「共同親権」も新しく導入されます。
これまでは離婚後はどちらか一方しか親権を持てませんでしたが、今後は話し合いによって「父母が一緒に親権を持つ」
こともできるようになります。
☑ほかのポイント
- 未払いの養育費は、財産を差し押さえやすくなるようなルール(一般先取特権)が新しく作られます
- 今まで通り、家庭裁判所の「養育費算定表」を使って個別に金額を決めることもできます
☑まとめ
「法定養育費制度」は、養育費の合意がなくても自動的に最低限の金額(月2万円案)を請求できる仕組みです。
ただし、金額はまだ決まったものではなく、今後変更される可能性があります。
さらに共同親権の導入により、両親が協力して子どもを育てる道も広がります。
2026年までにスタートする予定で、子どもの生活を守るための新しい制度として注目されています。
💬ラインはこちら⬇️

📱 電話:070-8490-2465
(受付時間:平日10:00~17:00)